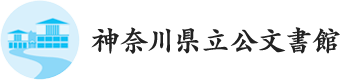神奈川県歴史資料所在調査
国内各地にある公文書館・文書館の多くでは、その地域の歩みを伝える歴史資料が集められ、大切に保存されています。
国立公文書館では徳川幕府から受け継いだ内閣文庫を所蔵していますが、当館においても神奈川県史を編集した昭和40年代に収集した資料や撮影した写真、さらにその後に受け入れた寄贈・寄託の古文書・私文書など、古代から現代に至る膨大な資料が保存されており、先人たちの生活や足跡の手がかりを示してくれる資料として、多くの方に閲覧利用されています。
例えば、江戸時代に名主や組頭などの村役人をつとめた家の文書には、今日の土地台帳に当たる検地帳、徴税令書である年貢割付状、その受領書としての年貢皆済目録、町・村勢要覧に当たる村明細帳、村の財政を示す村入用帳、戸籍謄本台帳である宗門人別改帳、人の移動証明通知に当たる人別送り手形など、今日の市町村役場における行政遂行のための文書と同じ役割を持つものがあります。
こうした歴史資料は今も県内各地に残されていますが、資料の劣化(カビや虫による損傷)や都市化の波によってそれまでの保管場所を失い、単なる紙屑として処分されていくケースも少なくありません。
当館では県内に残された歴史資料の散逸防止を目的に、所在調査を実施しています。これは歴史的公文書・古文書等を県民の共有財産として永く後世に伝えるため、収集・保存や調査研究を規定した神奈川県立公文書館条例等に基づいた調査で、資料保存の第一段階として欠かせないものです。
所在調査では当館職員が県内各地に赴いて所在の確認に努め、資料の発掘や整理にあたりますが、整理手順は一般的に次の流れとなります。
- 資料保存用の中性紙封筒に、資料の表題名・内容・年代・差出人・受取人等の必要事項を記入する。
- 資料を中性紙封筒に入れる。
- 項目や通年にしたがって袋に番号をふる。
- 資料の番号順に目録用紙に記入する。
- 作業終了後、資料の内容と今後のアフターケアについての説明を行う。
- ここで作成した目録を「神奈川県歴史資料所在目録」として刊行する。
時代の流れの中に、過去を伝える知の遺産が次々と薄れゆく現在、古文書等の歴史資料の保存は急務といえましょう。
私たち公文書館職員と一緒に資料の保存について考えていただけたら幸いです。